黄昏の空
□椿
1ページ/1ページ
椿
美しかった紅い髪は乱れ、
しなやかな筋肉がついていた手足は干からびた骨と皮になり、
カサついた唇からこぼれ落ちるは、同じくカレタ声だった
その姿から誰が想像できようか。
彼女があの美しかった少女とは。
誰が想像できようか。
彼女がこんな終わりを迎えると。
どんなに優秀な官をむかえ、どんなに信の篤い仲間をむかえても、終焉は変えられない。
王が辿り着く先はただ一つの道なのだから。
「どうか、主上…」
゛―――思い直し下さい。″
その言葉を何度告げたか。
「なぁ、懐達という言葉を知っているか?」
「懐達―…達王を懐かしむ、もう、聞かれぬ言葉ですね」
そう。
知らぬ者が多いほど、時を重ねてきた。
達王の治世を上回る程に。常乱の国だった慶国に平安を与えたと謂われる位に。
「私は懐達という言葉に正直うんざりしていたんだ。」
本当に嫌そうに女王は一息ついて口元を歪めた。
「自分たちは懐達、懐達と過去を懐かしんで比べるくせに、私が故郷を懐かしむのは許せないらしくてな。とんだ災難だ。しかも、女王だ、胎果だと煩くてかなわん」
゛だから女王は――″
゛懐達″
一度消えた言葉が再び水面下で囁かれ始める。嘆きと蔑みを共に。
けれど
「今ならまだ間に合います」
国の状態は酷い。
けれど、
縋り付きたいのだ。
この方なら何とかしてくれる――そう思えてならないから。
この王は希望だった。
無くしてしまうのはあまりに恐怖、余りに―――
「惜しまれて亡くなる王などいらない」
目の前の官の心を読んだ様に王は言い放つ。
「とことん怨まれて、憎まれて沈まなくては。」
あぁ…。地位も名誉もこの方の前では無意味。
「希望は次王にさえあればいい」
目的の為には己さえも捨てられる人だ。
故に王であり続け、王故に滅びゆく。残酷なまでに。
「そうだろう?」
そう、言ってのけたこの方を王と呼ばずに何と呼べばいいのだろう。
「主上――」
「下がれ」
おしゃべりは終わりだ、と遮って、王はその細い体を引きずる様に立ち上がる。
「もう、ここには来ないでいい」
それを意味することはただ一つで。
握った拳が震える。
「そうだ。もし、牢の中にいる浩瀚という男に会ったら伝えてほしい」
王の右腕だった冢宰は、失道直後に王自身の勅令により免職され牢にいれられた。
それにより、官吏は絶望し、民は諦めた。
この王を見捨てた。
だが、解ってしまった。
今更ながら王の真意が。
恐らくは、その身を護るために。大切な官僚を無くさぬために。
この王は自分の元から遠ざけたのだ。
罪は《全て》王にある。
共に支えた官僚あってこその王だと知っている官吏でさえ、冢宰を罷免したことで、そう思いこんだ。
…思いこまされた。
恨みの向かう矛先は王のみにして。
もし、共に支えた官吏に恨みが及ぼうとも、牢の中では手の出しようがない。
すべては国の為に。
気付いて、しまった。
―――――王よ!!
何か言おうと顔を上げたのと、王の言葉は同時に。
「国葬など無用。」
――…全ては次王の為に使え。
答え(いらえ)は出来ない。ただただ深く頭を下げる事で己から溢れる嗚咽と涙を隠した。
それしか出来なかった。
END
灰色の空の下
紅い椿がポタリと落ちた
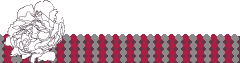
.